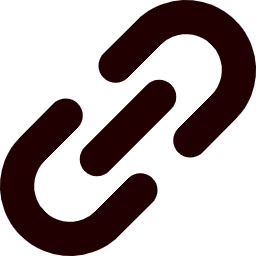お疲れ様です。
しらせです。
休日、家に引きこもってたら急にFreeNASが恋しくなったので動かして遊んでみました。
次期バージョンではTrueNASに名称変更される旨もアナウンスされているFreeNASですが、ブロックストレージとしてのiSCSIからファイルストレージとしてのNFSやSMB、AmazonS3ストレージまで多彩な使い方ができるのが特徴です。
以前FreeNAS8系を触っていた時代からもう3つもメジャーバージョンが上がっていたのですね。
今回は「FreeNAS-11.3-U2.1」を試してみます。
TrueNAS - ja.wikipedia.org
https://ja.wikipedia.org/wiki/TrueNAS
もくじ
インストール
今回基盤はWindows10付属のHyper-vを使います。
ベースとなるマシンのメモリサイズは8GBじゃないと動かないです。
OS領域としてのディスクサイズは64GBにしてみます。
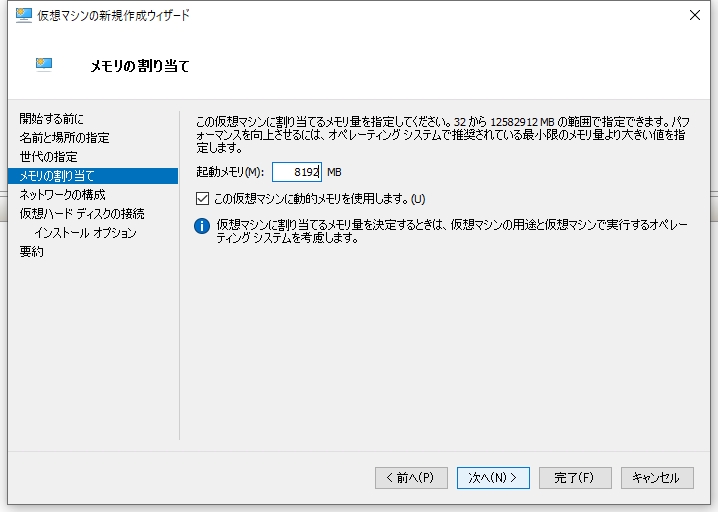
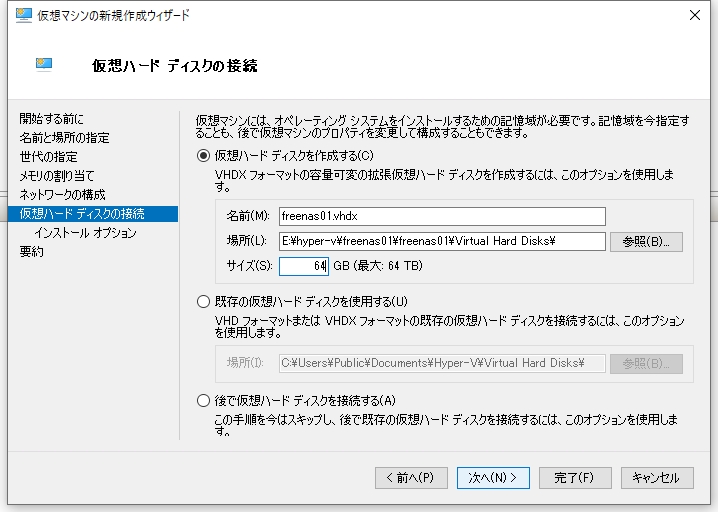
ディスクイメージからマウントしてインストールをはじめます。
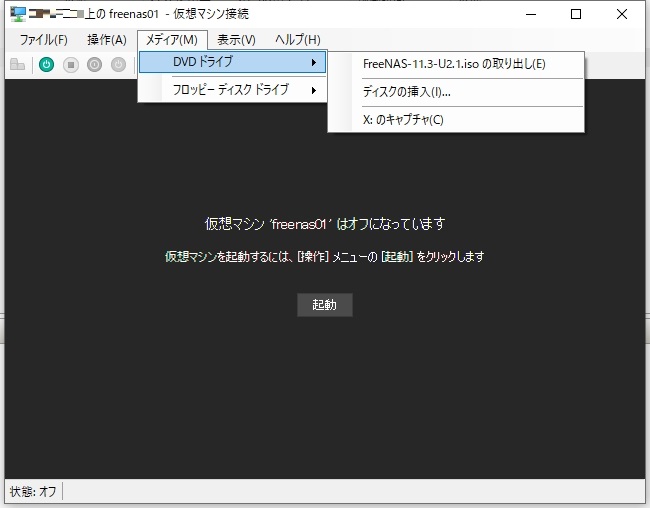
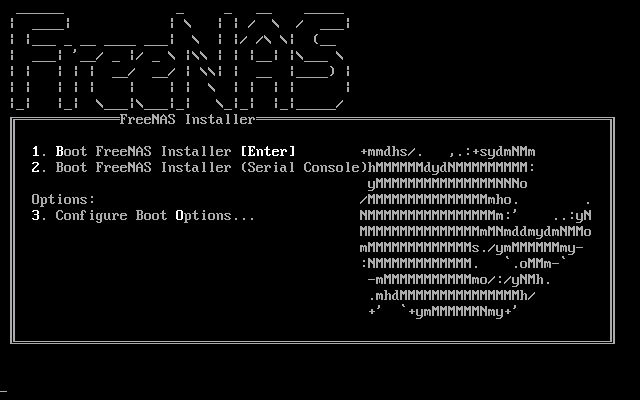
この辺りは昔と全く同じですね。
内容もシンプルでわかりやすい。
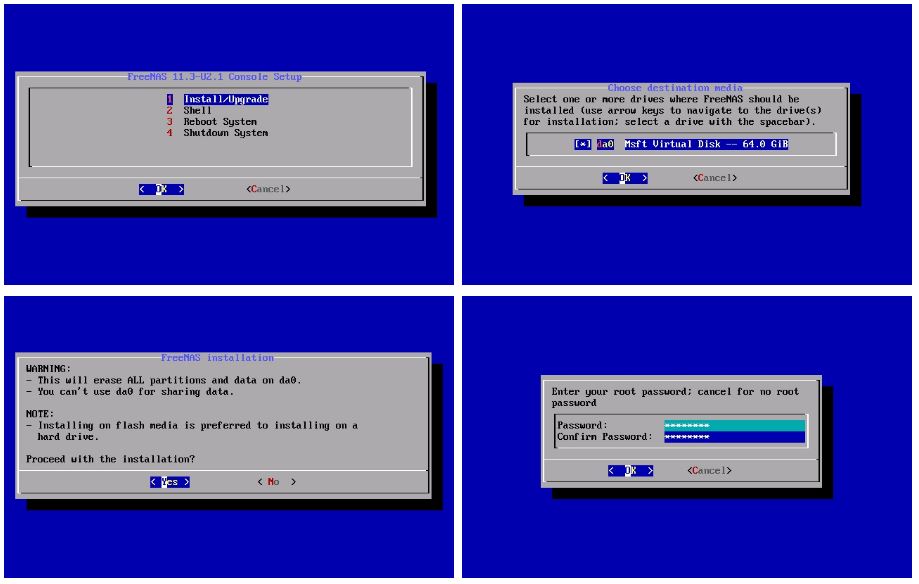
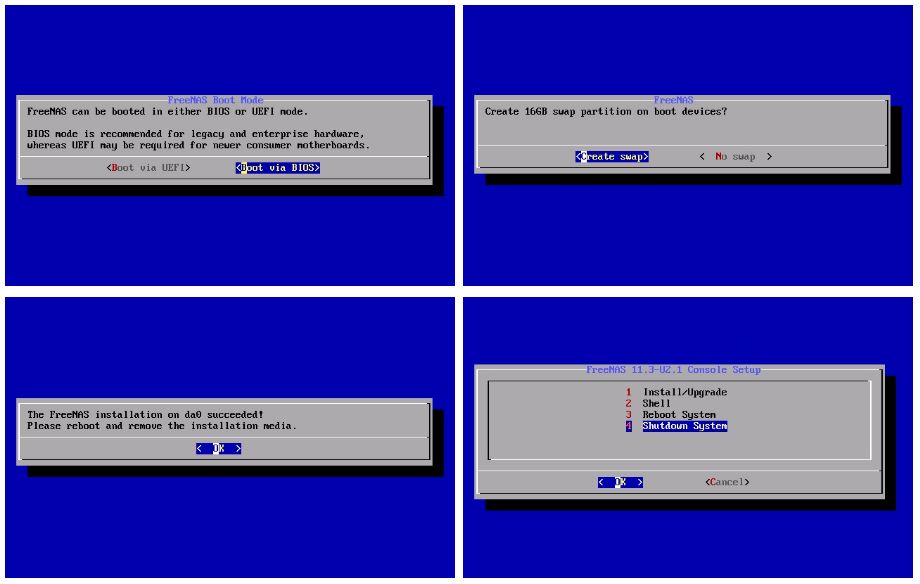
インストール後の初回起動で死。
BIOSだと微妙にうまくいかないのでUEFIで再チャレンジ。
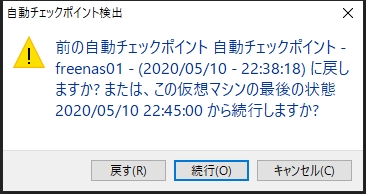
続行すると普通に起動する。
IPアドレス、DNSくらいは設定しておく。
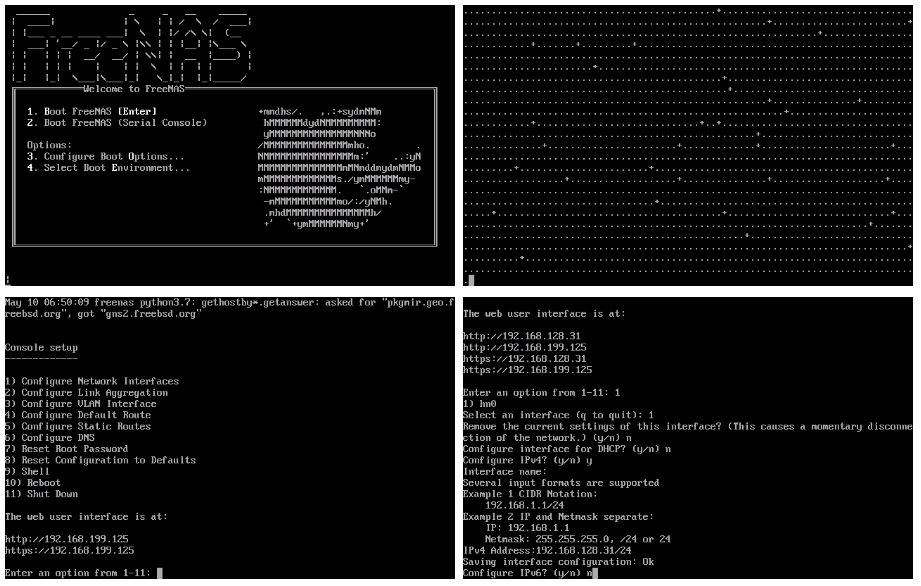
まずUIめっちゃ進化してる。(気がする)
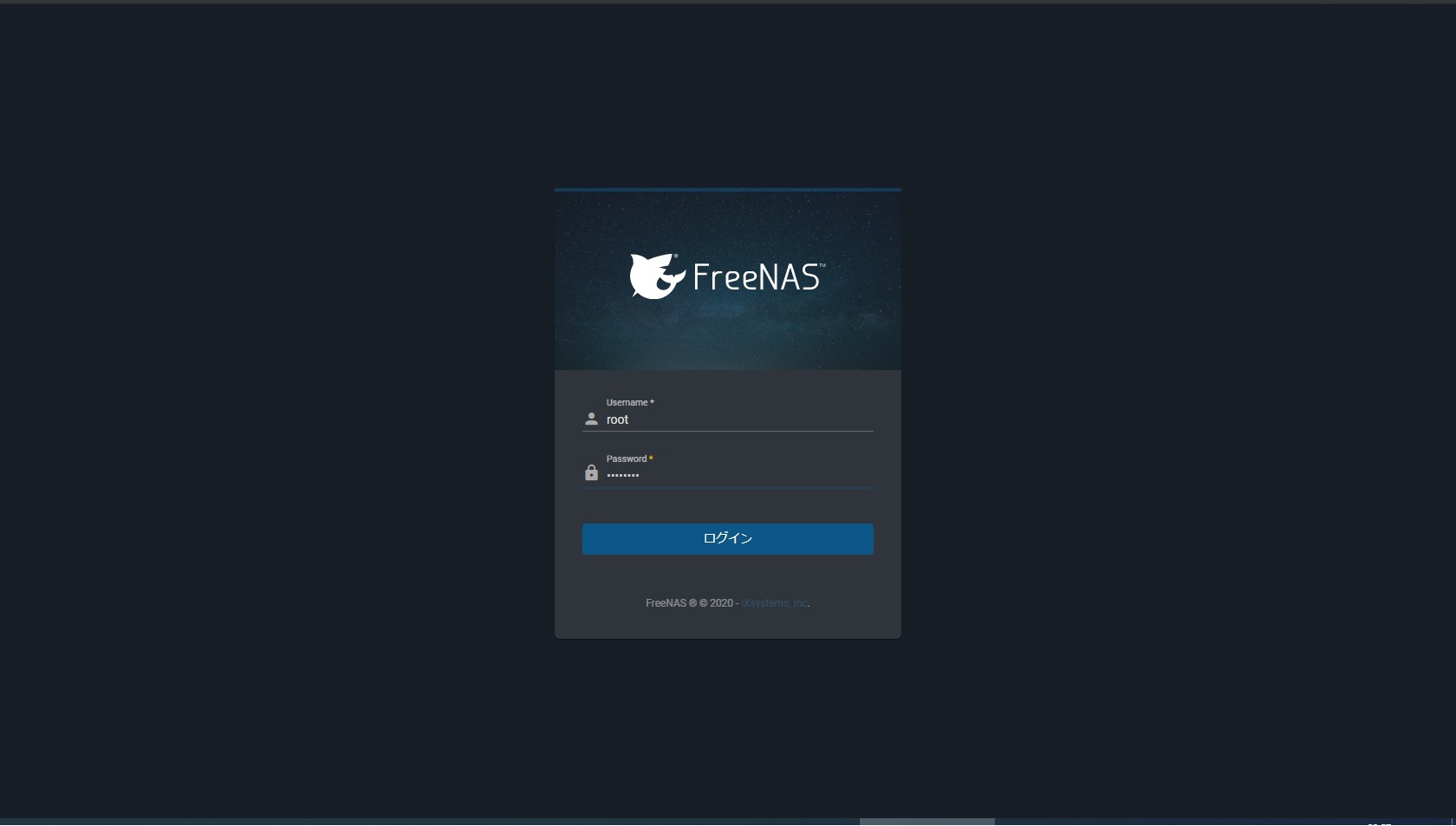
めっちゃ進化してた!
iXsystems。
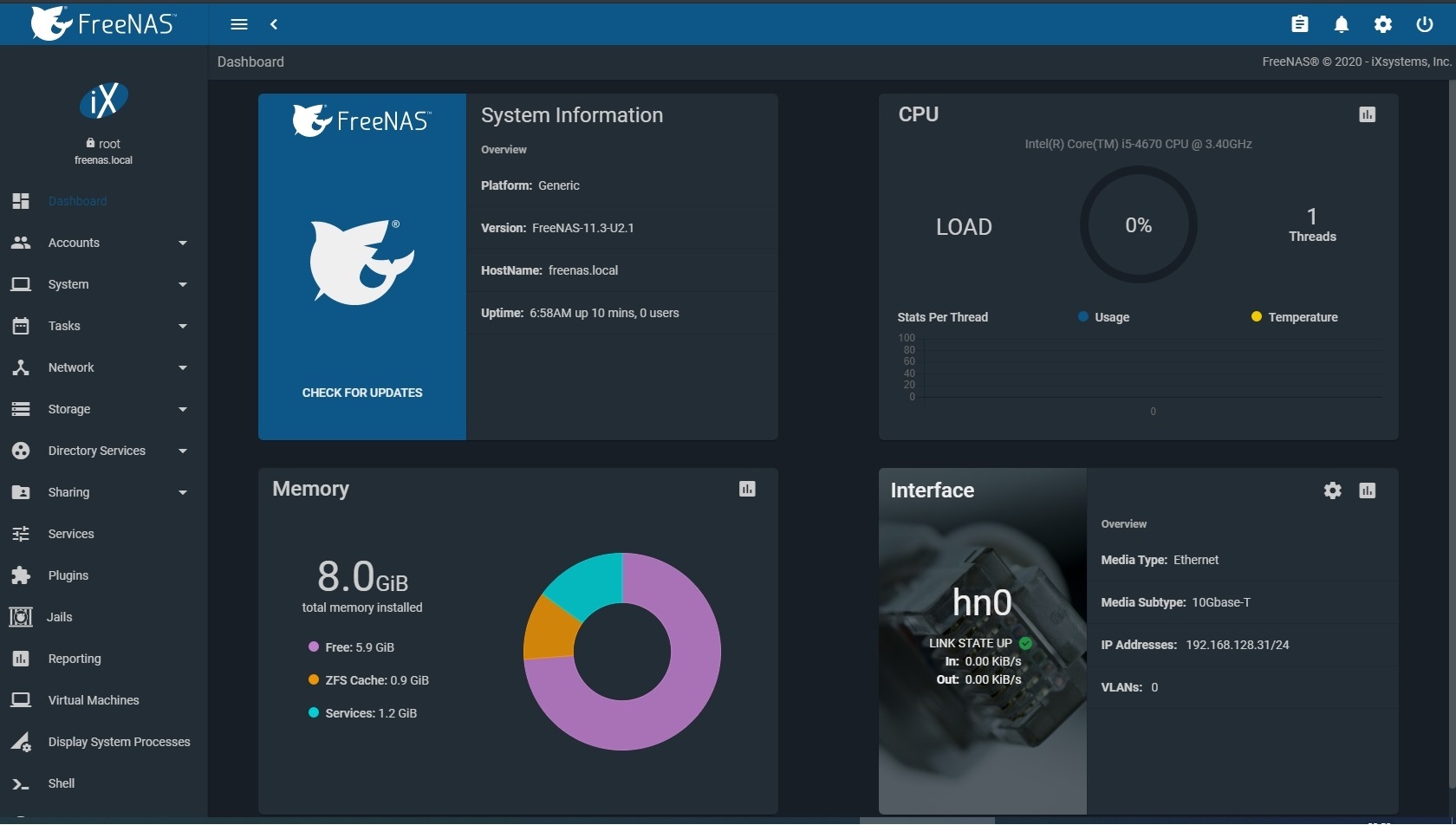
とりあえず言語は日本語にしてみましょうか。
ところどころ英語のままですが表現に特に変な感じはありません。
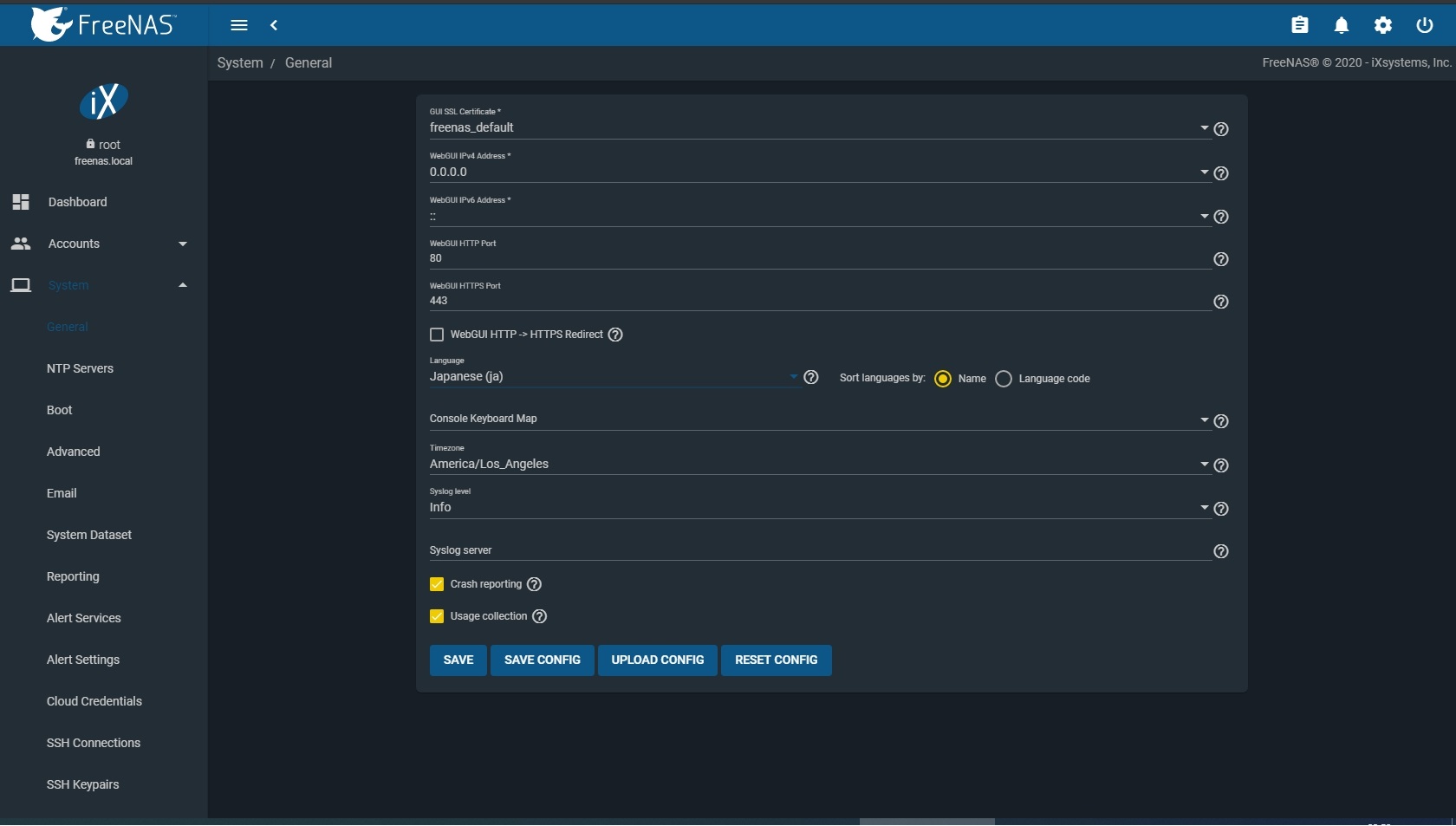
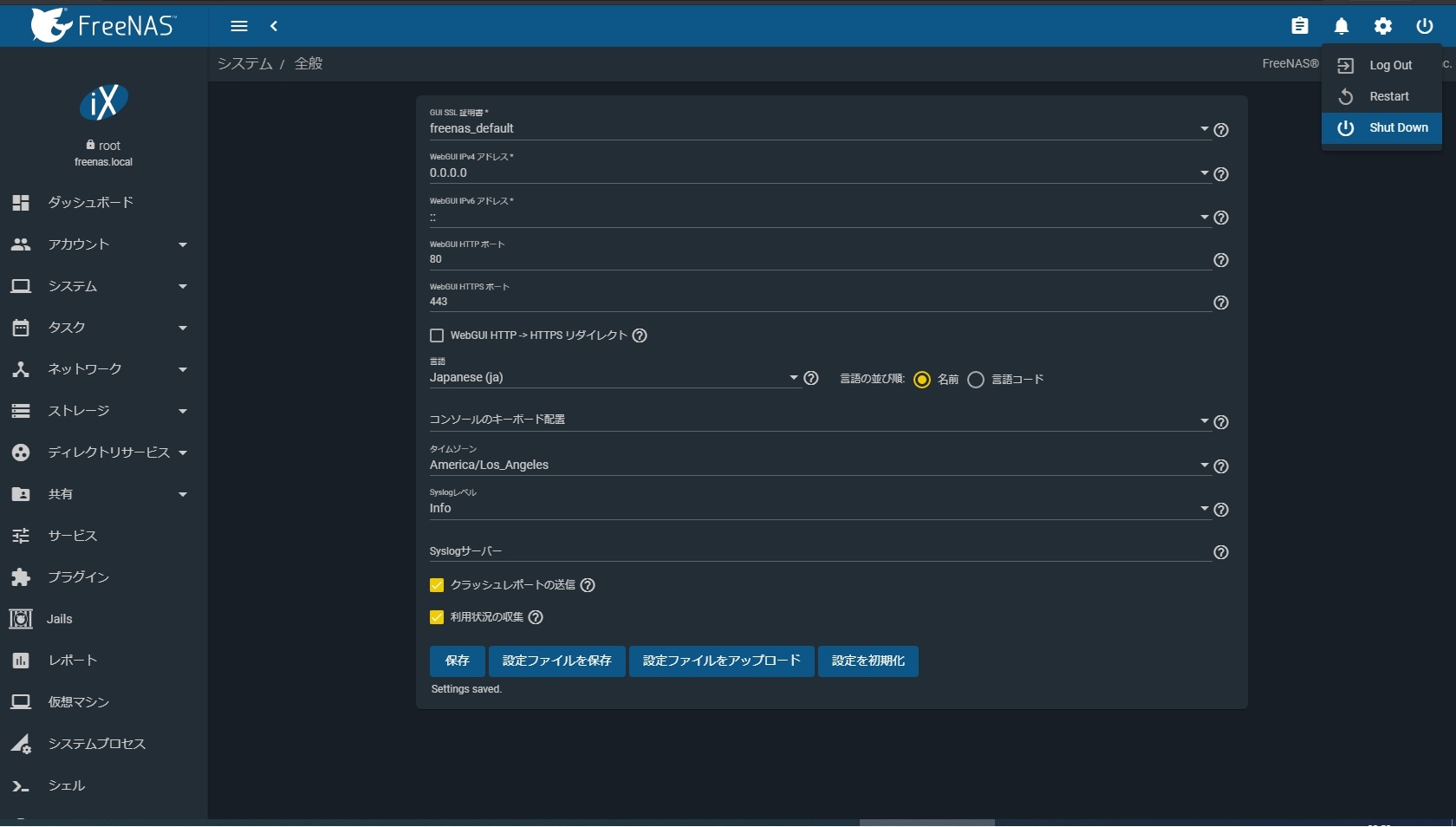
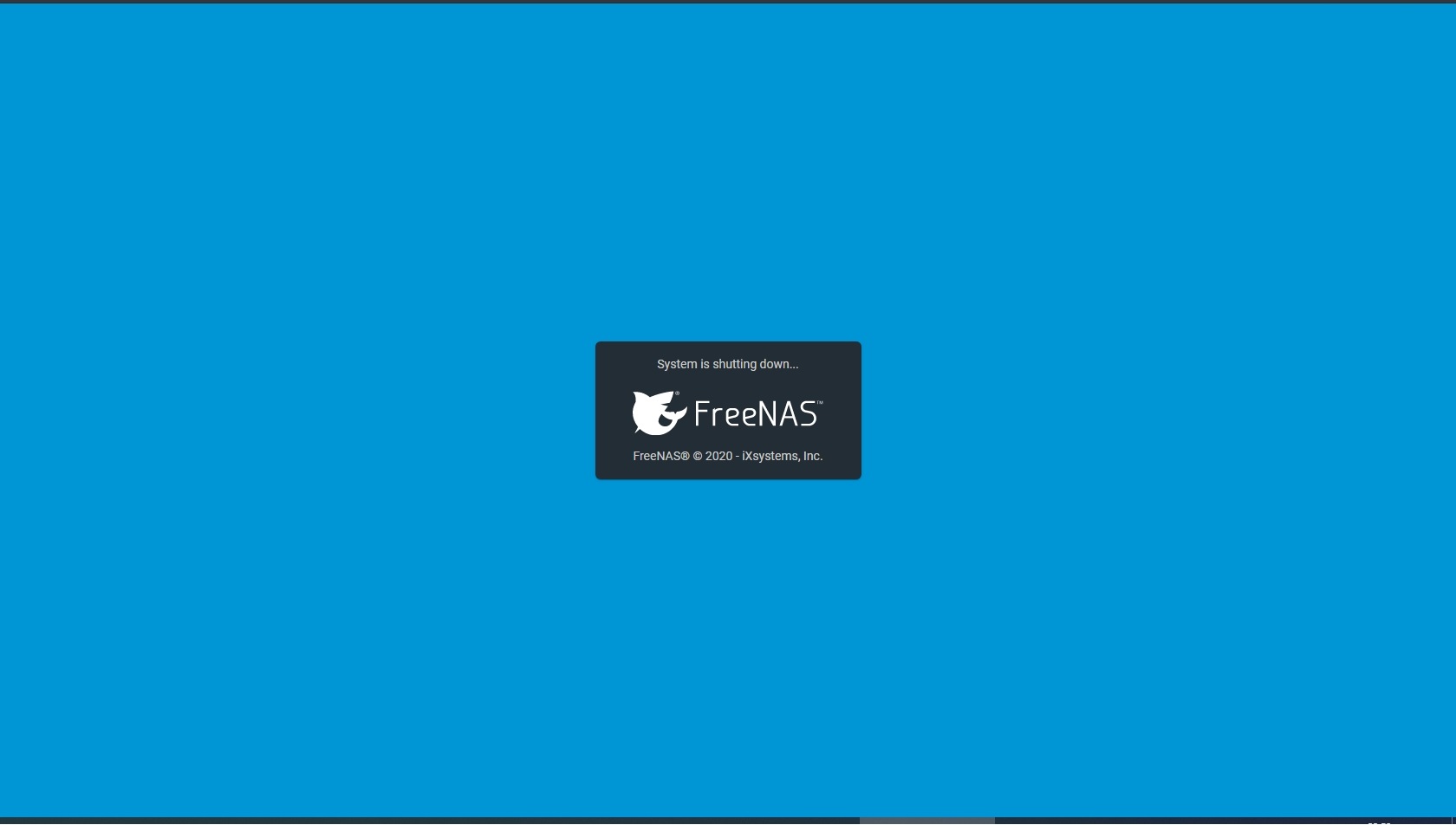
ディスク追加
ストレージなのにOS領域しか積んでないとかつまらないのでディスクを6本くらい追加してみます。
シャットダウンしたFreeNASに対して、SCSIコントローラーにディスクをモリモリ乗っけていきます。
IDEはディスク1つしか追加できないのでデイジーチェーンが可能なSCSIに変更です。
ディスクの初期化に時間がかかるので容量は可変です。
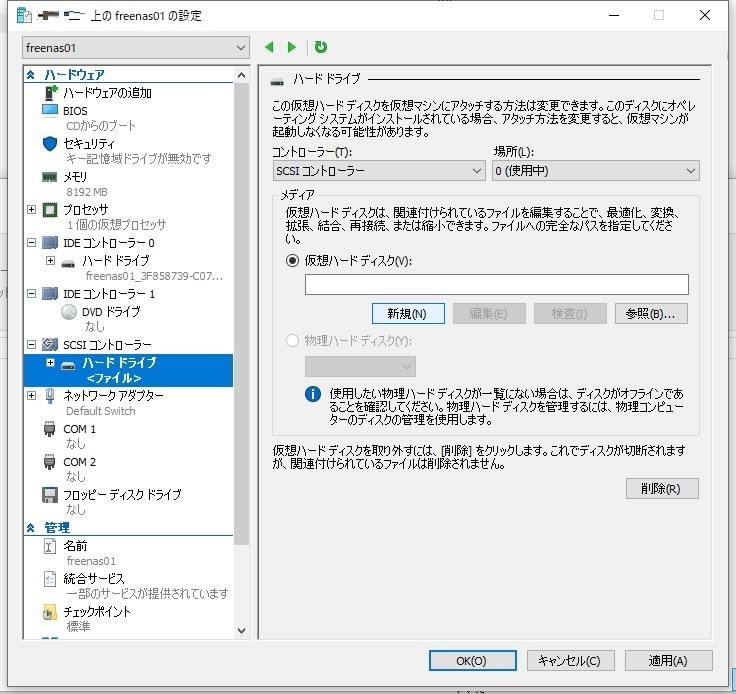
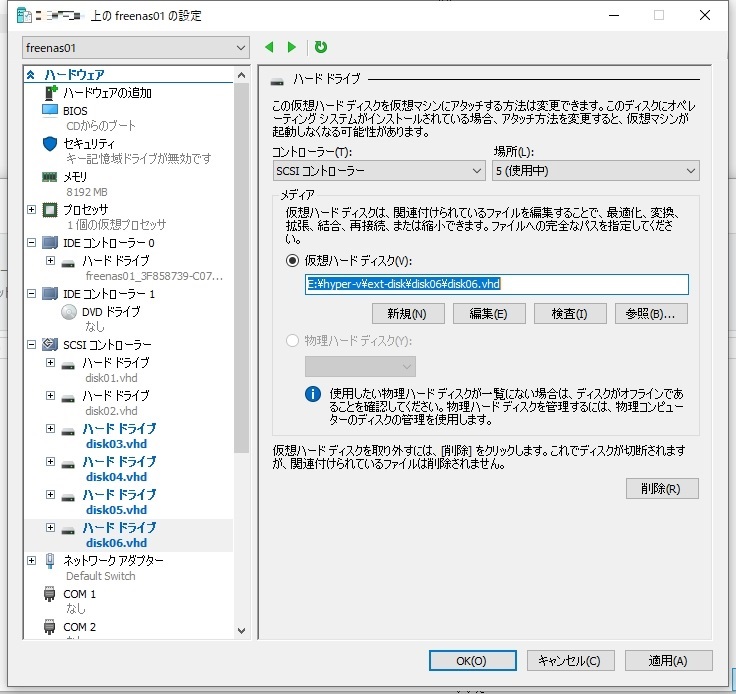
起動すると、、、
6本ちゃんと認識されました。
モデルのMsftのFTって何の略でしょうね。
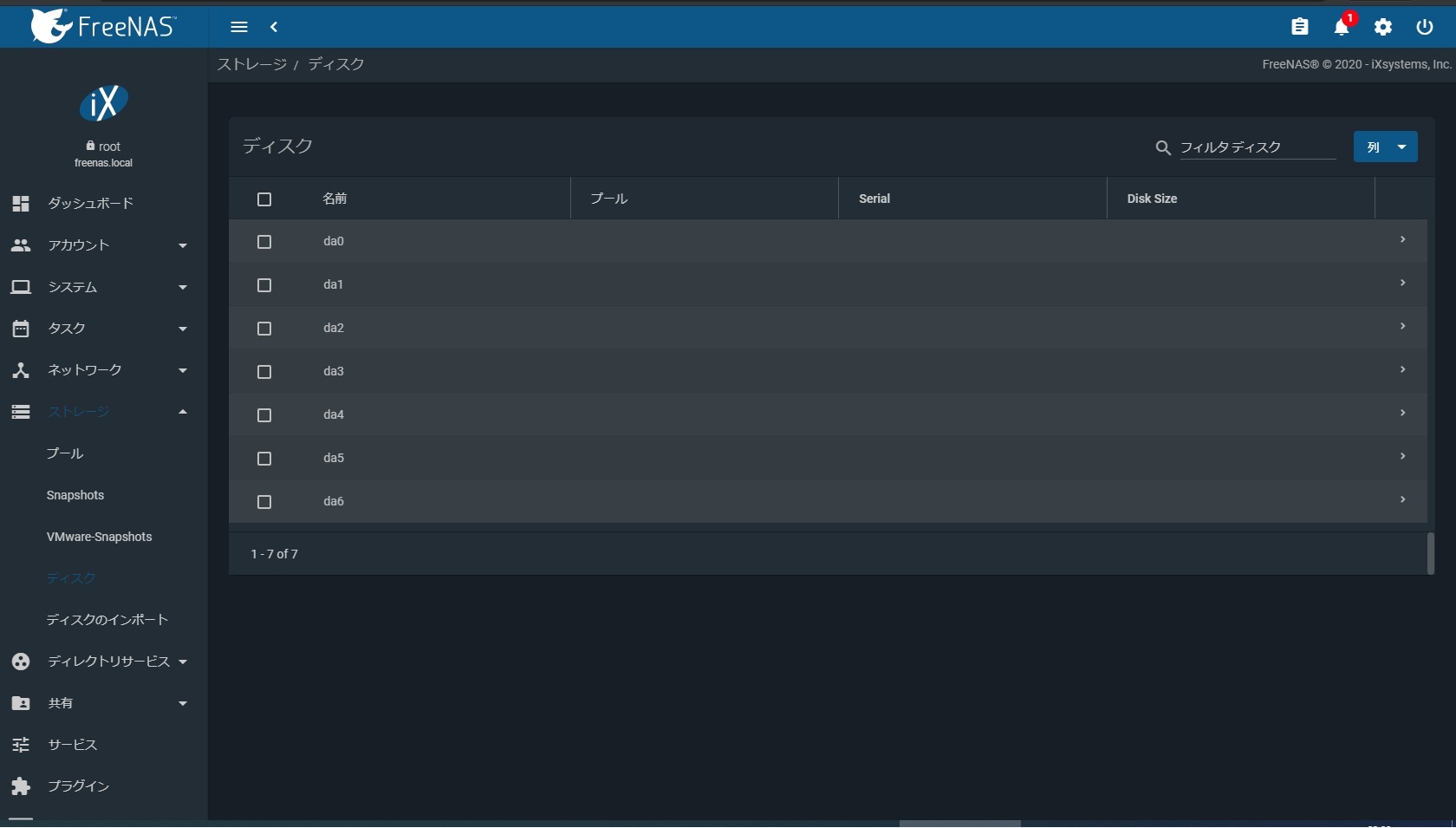
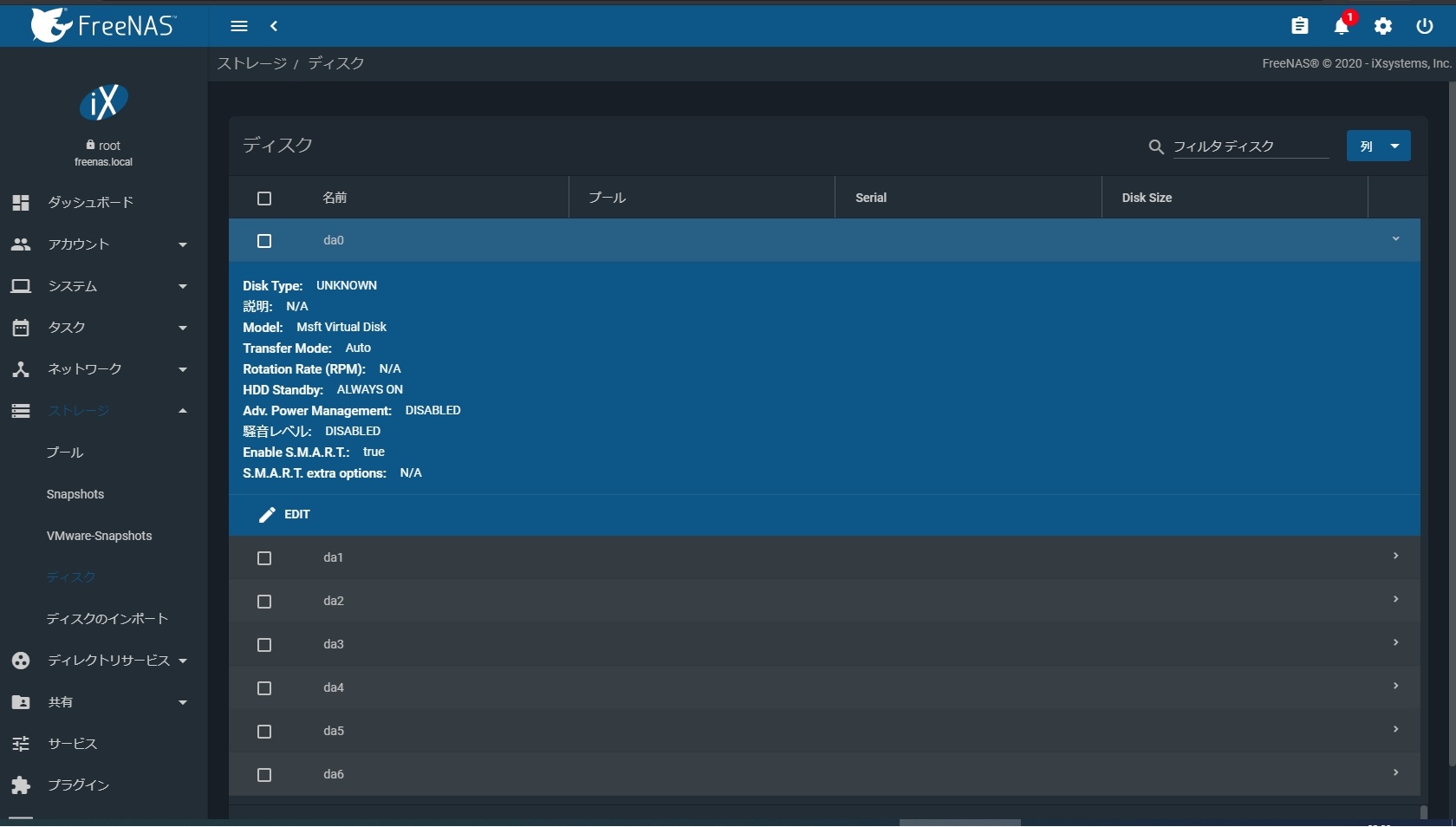
プール作成
ディスクを追加しただけでは使えないので、ディスクを束ねてデータ領域として扱うための「プール」を作ります。
複数のディスクを束ねて1つの領域として扱うことで、物理的な制約(ディスク1つだと壊れてデータが消えたりする)を回避できます。
いわゆるRAIDですね。
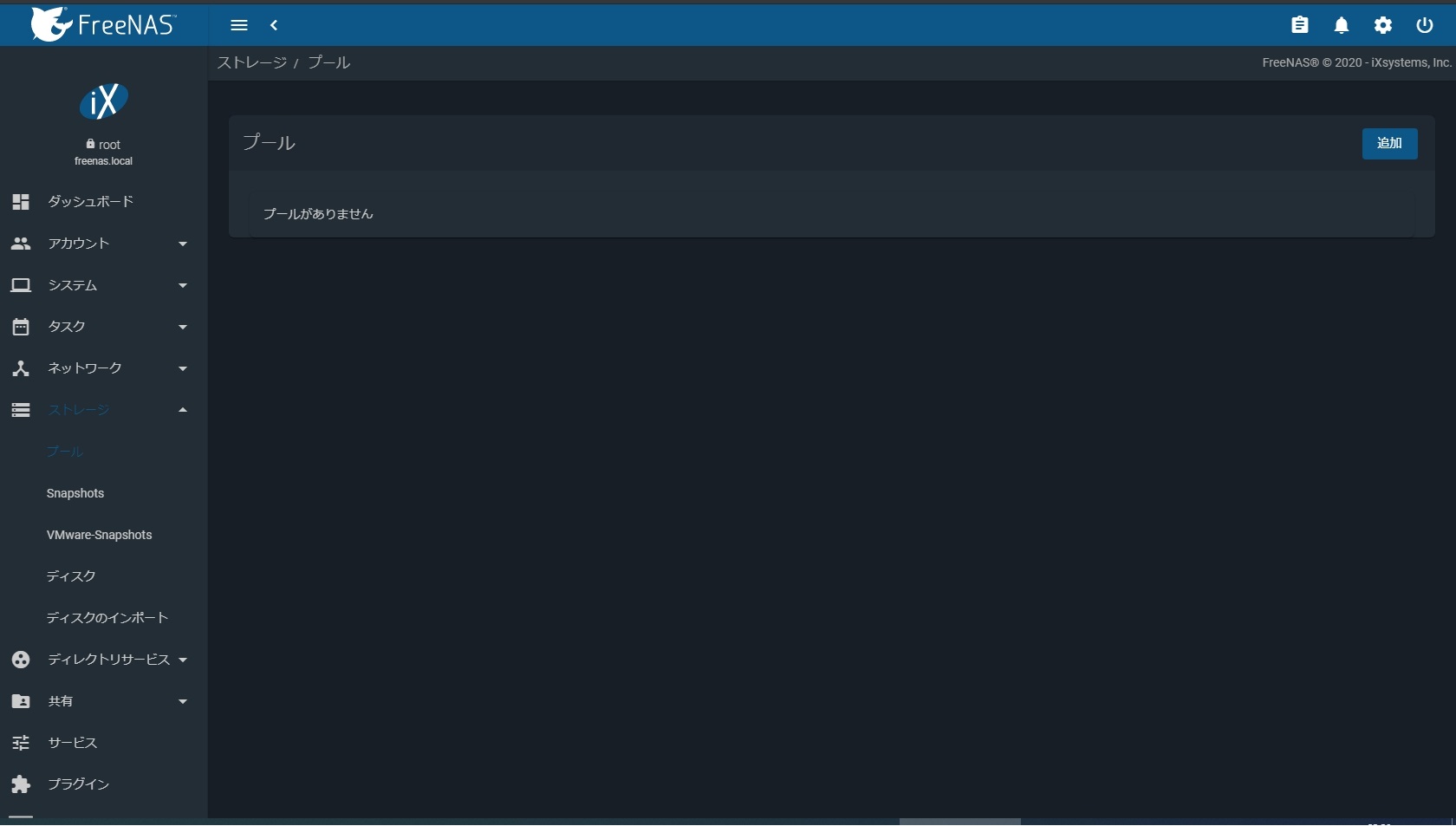
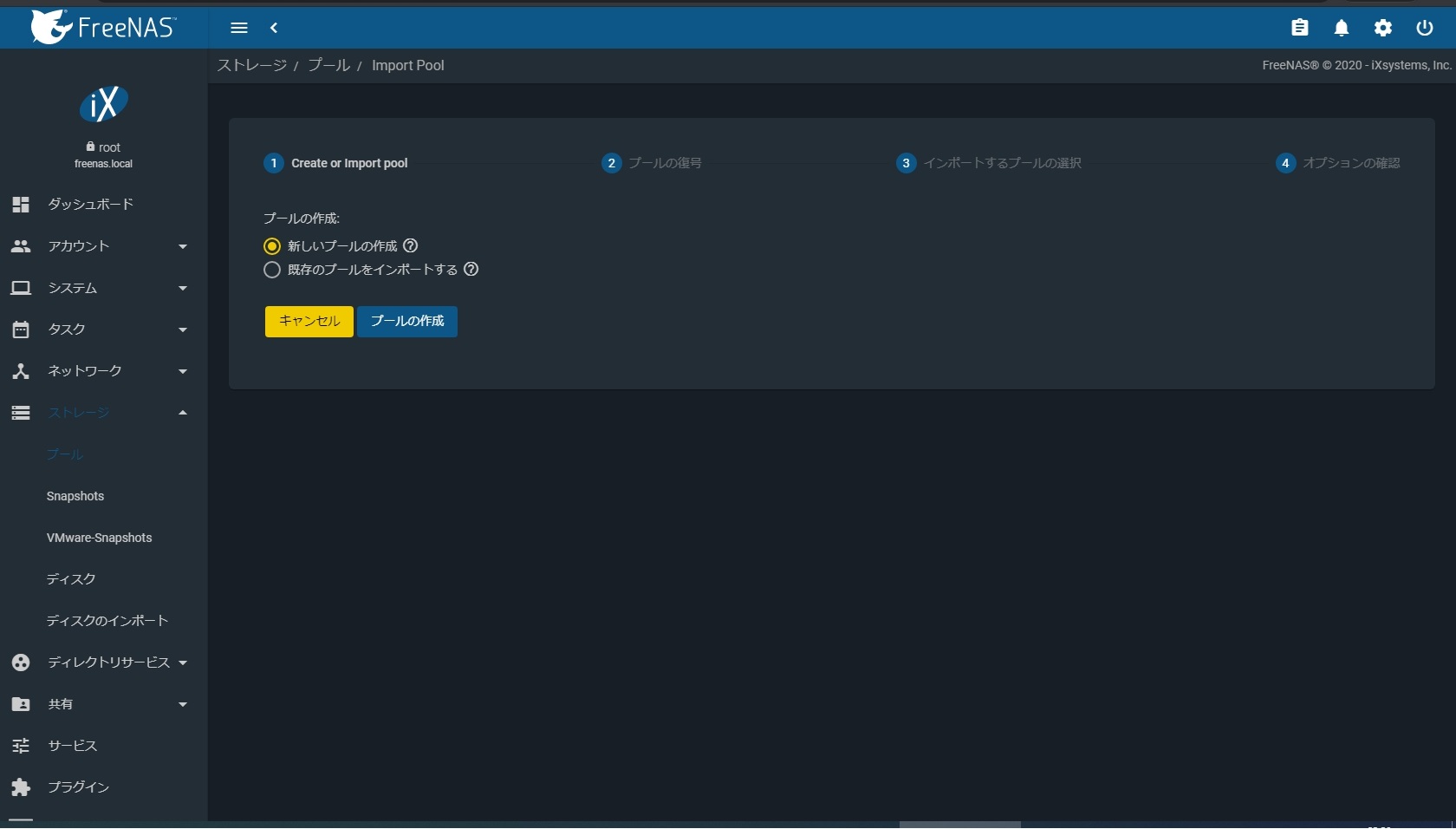
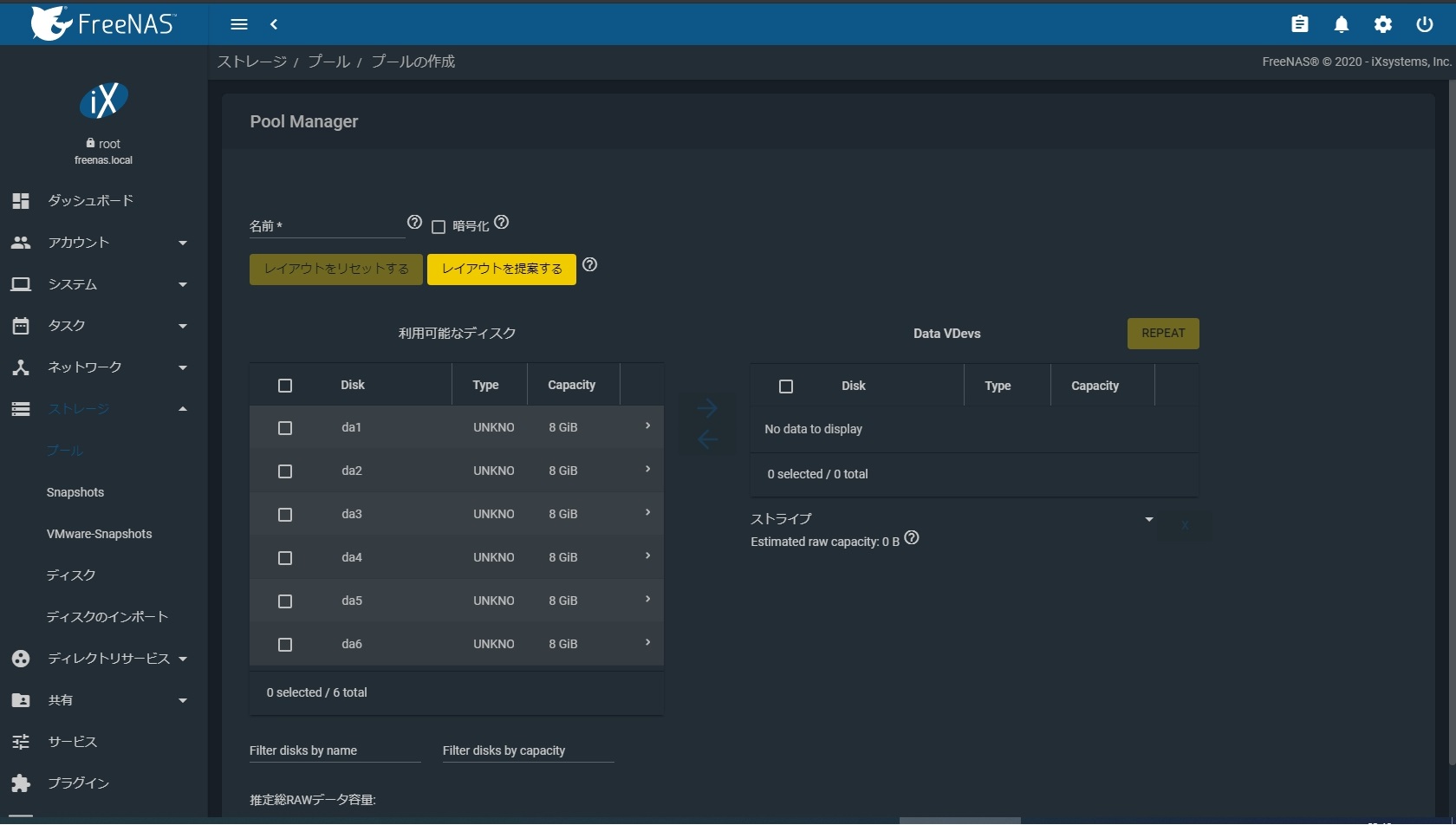
4つは、データが保存される領域として使います。
残り2つは、4つのディスクが壊れた時用のスペアとして割り当てます。
RAIDはz2を指定しています。
デュアルパリティなので実質ディスク2本分が使えないと思えばいいでしょう。
操作がすごくわかりやすい。
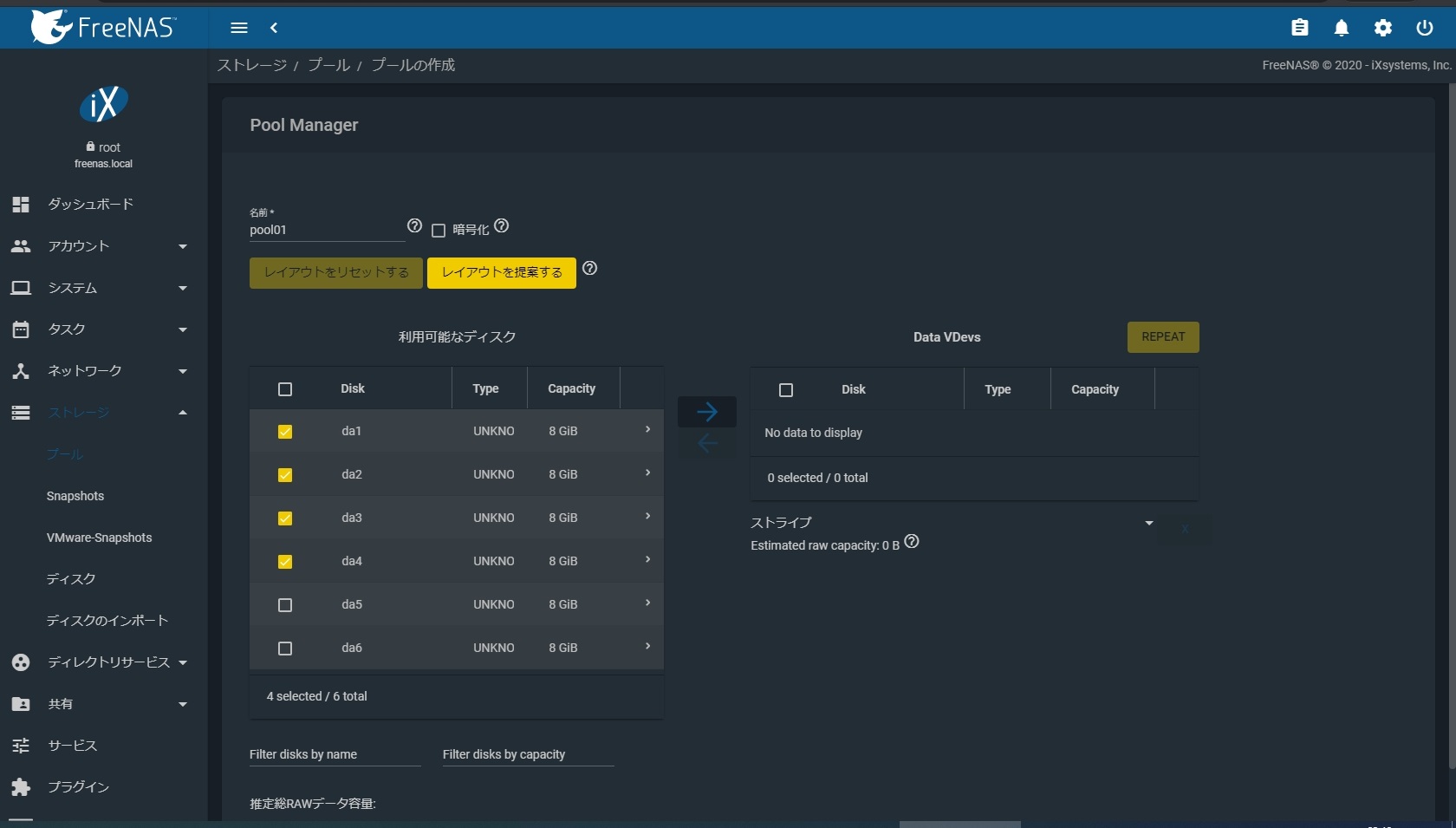
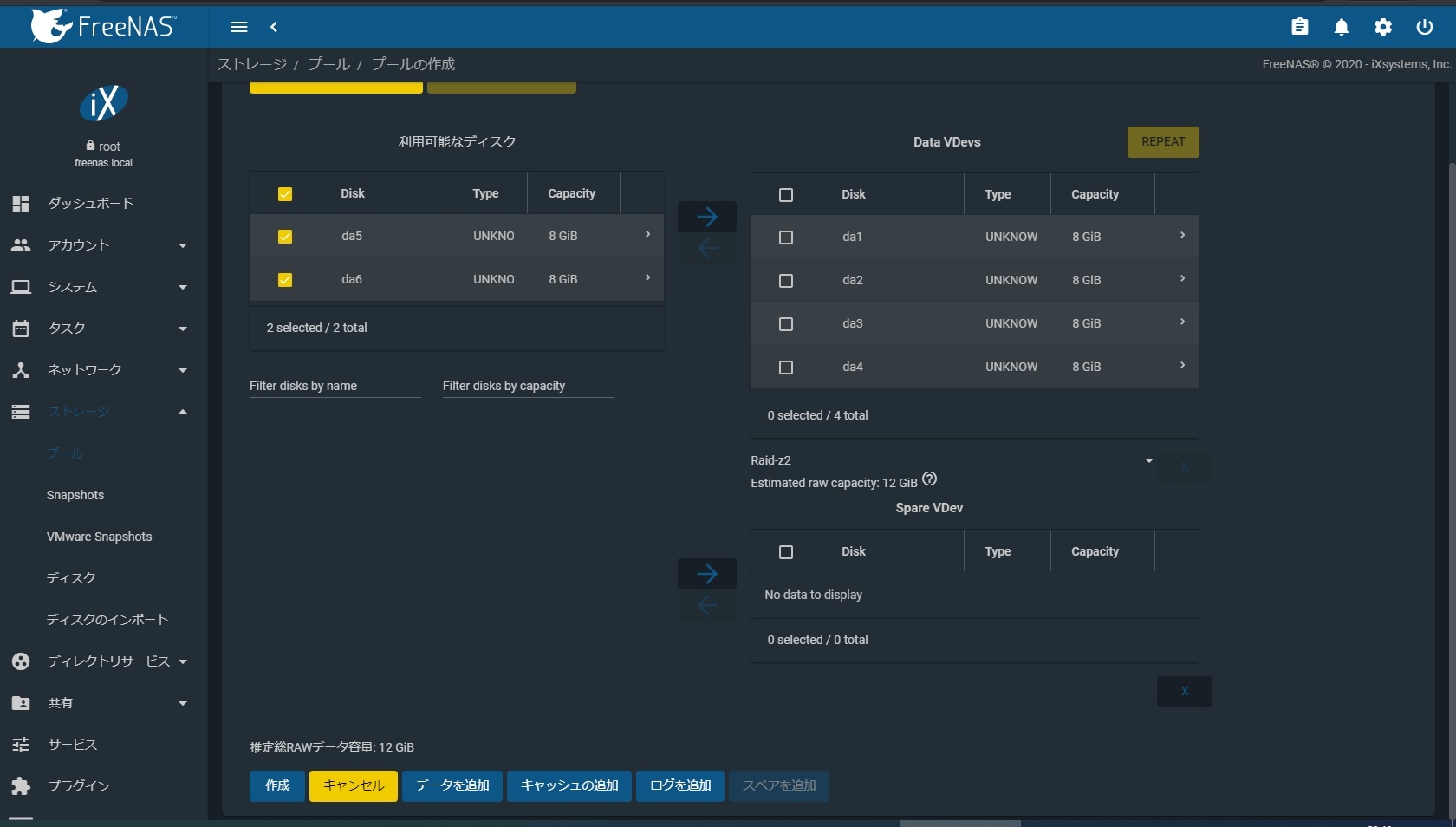
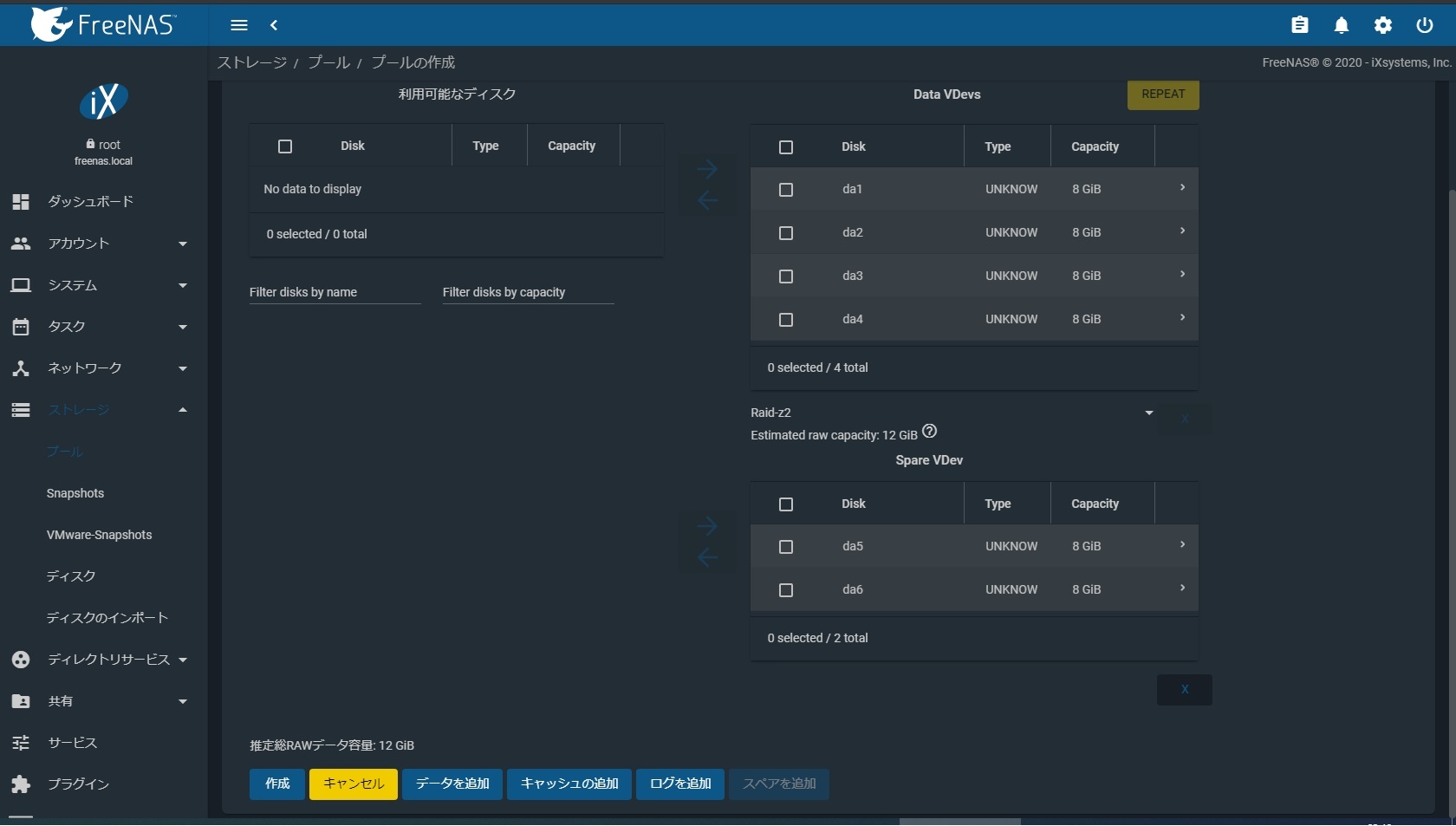
続行するとすぐにプールができました。
もちろんディスクは初期化されます。
8GB x (4-2) で16GB使えるかと思ったら、11GBちょっとしかない。
結構効率悪そう。
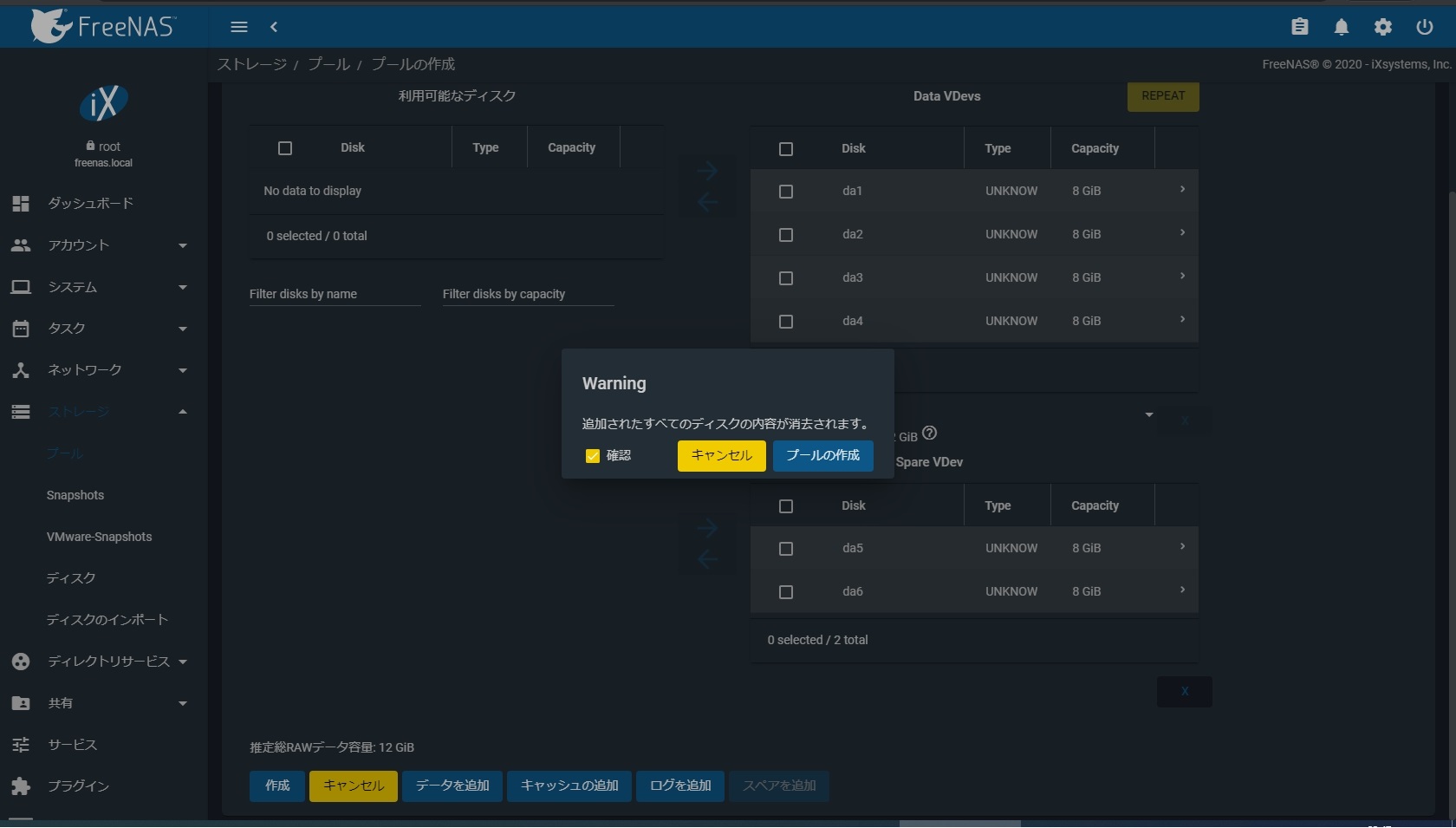
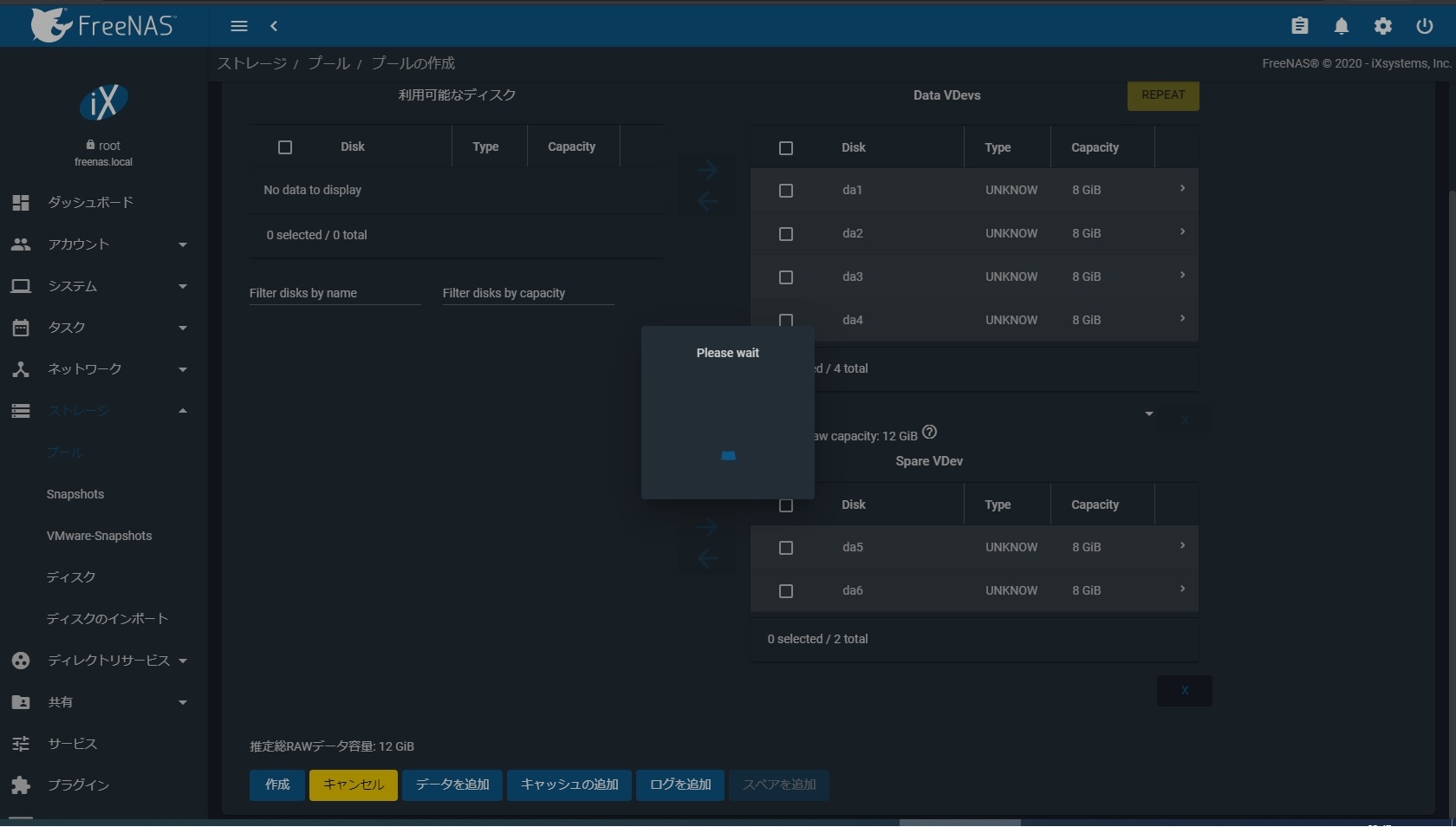
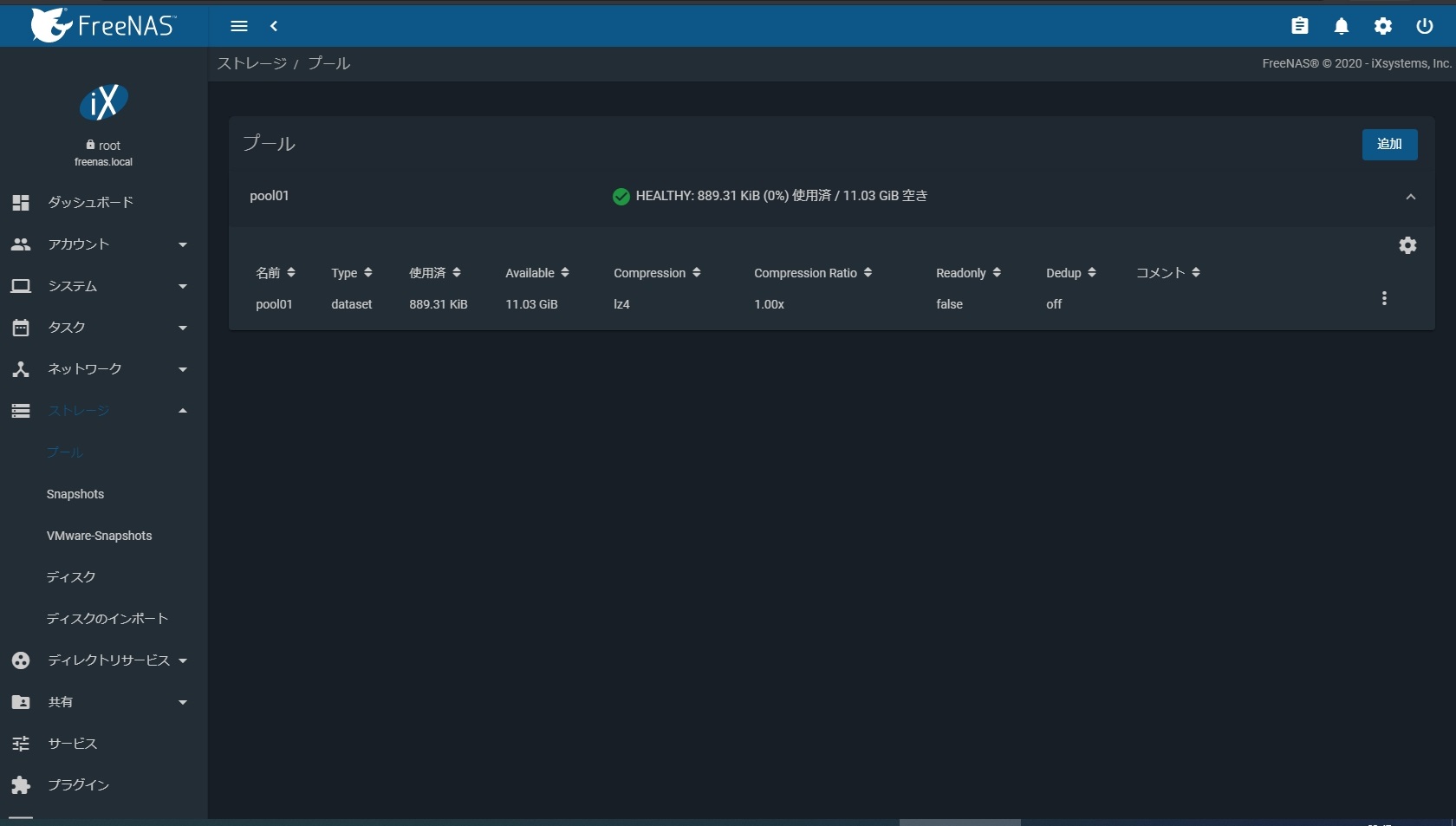
画像添付が多くなるので続きは次回へ。
次回はユーザー作成やSMB共有、ActiveDirectory連携などをやってみる予定です。
以上、お疲れさまでした。


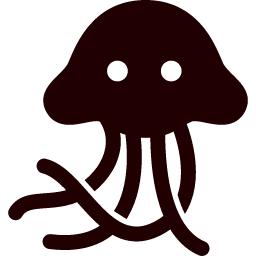 しらせ(HN)
しらせ(HN)